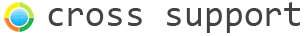ごあいさつ:年度末に向けて、光熱費が気になる季節です
気がつけば、街中にはイルミネーションや歳末セールのポスターが増え、「今年もそろそろ終わりか…」という空気が漂ってきました。オフィスや店舗でも、暖房の稼働時間が少しずつ長くなり、同時に「今月の電気代、どれくらいになるだろう?」と請求書が気になる時期ではないでしょうか。
ここ数年は、電気料金の値上げや、ニュースで取り上げられる「電力不足」「電気・ガス料金の補助金」といった話題が続き、経営者や総務ご担当者にとっても、電気料金は無視できないコスト項目になっています。
そこで今回は、今の電気料金トレンドをざっくり押さえつつ、経営者・総務の立場で「まず何から手をつければいいのか」を整理してお伝えします。
今押さえておきたい電気料金トレンド
1. この数年、電気料金の世界で何が起きていたのか
まず、ここ数年の「大きな流れ」だけざっくり押さえておきましょう。
- 2021〜2022年:ロシアによるウクライナ侵攻や燃料価格の高騰、急激な円安を背景に、卸電力市場(JEPX)の価格が急騰。企業の電気料金にも大きな影響が出ました。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
- 新電力の撤退・料金見直し:市場価格の高騰に耐えきれず、事業の休止・撤退を余儀なくされた新電力が増加。残った事業者でも、料金改定や燃料費調整額の上限撤廃が相次ぎました。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
- 政府による電気・ガス料金の支援:負担増を抑えるため、2023年以降、電気・ガス価格激変緩和対策や電気・ガス料金負担軽減支援事業が段階的に実施され、家庭・企業の請求額が自動的に値引きされました。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
つまり、「市場価格の乱高下 → 電気料金の上昇 → 政府による補助金で一部緩和」という波が、ここ数年ずっと続いてきたイメージです。
2. 今の電気料金は「高止まり+じわじわ変動」の局面
直近では、燃料価格の落ち着きもあり、2025年の電気料金は「急激な値上がりは一服し、横ばい〜緩やかな変動」とみる専門家が多い状況です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
実際、法人向けの平均単価を見ると、特別高圧・高圧ともに2025年夏時点で前年よりやや下がっている一方、依然として10年前と比べれば高い水準にあります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
加えて、
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(いわゆる再エネ賦課金)の動向
- 燃料費調整額の上限撤廃による、市場価格の影響の受けやすさ
- 政府の補助金(激変緩和・負担軽減支援)がいつまで続くか
といった要素が重なり、「長期的には高止まりリスクが続く」というのが、現在の電気料金トレンドのざっくりとした見立てです。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
3. 電力自由化と新電力のシェア拡大
2016年の電力小売全面自由化以降、日本の電力小売市場には多くの新電力が参入しました。2025年時点で、小売電気事業者の登録数は700社超にのぼり、市場全体の販売電力量に占める新電力のシェアは約2割程度まで拡大しています。
低圧(家庭・小規模事業者)では約25%前後、高圧でも2割前後を新電力が占めており、料金・サービスの選択肢として、もはや「一部の先進企業だけの話」ではなくなってきました。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
その一方で、新電力の事業撤退も経験した私たちは、「安さだけで選ぶのではなく、リスクも含めた見極めが重要」な段階にきているとも言えます。電気料金トレンドを理解するうえで、「自由化によって選択肢が増えた」という事実と、「市場価格リスクが見えにくくなった」という側面の両方を押さえておくことが大切です。
経営者・総務担当が取るべき具体的な対策
1. まずは「現状把握」と「単価の見える化」から
どんな対策も、現状把握なしには始まりません。まずは、直近1年分くらいの請求書・検針票を手元に集めて、次のポイントを一覧化してみてください。
- 契約種別(特高・高圧・低圧、従量電灯・動力など)
- 契約電力(kW)または契約容量(kVA・A)
- 1ヶ月あたりの使用電力量(kWh)
- 燃料費調整額や再エネ賦課金の単価
- 「基本料金」と「電力量料金」の割合
ここまで整理できると、「うちは使用量よりも基本料金の比率が高いのか」「単価そのものが高いのか」といったおおまかな傾向が見えてきます。
この作業だけでも、後で専門家に相談する際に話がスムーズになり、見積もりの精度も上がります。
2. 新電力・料金プランの見直しで“相場”に近づける
次のステップは、「いまの契約が相場から見て高いのかどうか」を確認することです。法人向けの平均単価や、同業種・同規模の企業がどの程度の単価で契約しているかを把握することで、「見直す余地」があるかどうかが見えてきます。:contentReference[oaicite:8]{index=8}
新電力や他社プランへの切り替えを検討する際は、次のような点をチェックするのがおすすめです。
- 提示されている単価(基本料金・電力量料金・割引条件など)は、現契約と比べてどれくらい差があるか
- 市場連動型プランかどうか(JEPX価格の変動をどの程度受けるのか)
- 契約期間・違約金・自動更新などの条件
- 過去の価格高騰局面で、どのような対応をしてきた事業者か(撤退リスク・信頼性)
「最安値を狙う」というよりも、「自社のリスク許容度に合った、バランスのよいプランを選ぶ」という感覚で検討されると、結果的に長く付き合える電力会社選びにつながります。
3. 契約電力(基本料金)を下げる:電子ブレーカー等の活用
電気料金のうち、見落とされがちなのが「基本料金」の部分です。多くの企業で、契約電力(kW)×単価で基本料金が決まりますが、この契約電力は過去1年間の最大需要電力(デマンド)やブレーカー容量を基準に決まっていることが一般的です。
ここで有効になるのが、電子ブレーカーの導入です。電子ブレーカーは、従来型ブレーカーよりも精度の高い管理が可能で、
- 一時的なピーク電流で過大な契約をしている
- 昔の設備構成のまま契約が見直されていない
といったケースで、契約電力そのものを適正化し、基本料金を下げる効果が期待できます。
もちろん、導入には現地調査や負荷状況の確認が不可欠ですが、「使用量を減らさなくても、基本料金の見直しだけでコストを削減できる」可能性があるため、電気料金対策として非常に相性が良い施策です。
4. 中長期の省エネ投資と「補助金の上乗せ活用」
最後に、中長期の視点で欠かせないのが省エネ投資です。高効率空調やLED照明、インバータ制御、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)などは、初期投資はかかるものの、数年単位で見ると大きな削減効果を生みます。
加えて、政府・自治体は、エネルギー価格高騰対策やカーボンニュートラルを後押しする補助金・助成金を継続的に実施しています。エネルギー価格支援のポータルサイトでも、最新の支援策の枠組みが紹介されていますので、電気料金対策とあわせてチェックしておくと良いでしょう。:contentReference[oaicite:9]{index=9}
ポイントは、「電気料金の補助金」だけでなく、「省エネ投資に対する補助金」も組み合わせて検討することです。これにより、単なる一時的なコスト軽減にとどまらず、「使い続けるほど効いてくる」持続的なコストダウンが実現しやすくなります。
まとめ:トレンドを押さえつつ、自社に合った電気料金戦略を
今回は、経営者・総務ご担当者向けに、電気料金のトレンドと、今取り組むべき対策のキホンをお伝えしました。
- ここ数年、電気料金は市場価格の乱高下と補助金による緩和が続く「高止まり」の局面にある
- 電力自由化で新電力が増え、選択肢は広がった一方で、事業撤退や市場連動リスクも顕在化している
- 対策の第一歩は、現状の契約内容と単価の「見える化」から
- 新電力・料金プランの見直しだけでなく、電子ブレーカー導入などによる契約電力の適正化も有効
- 省エネ投資と各種補助金を組み合わせることで、中長期的なコストダウンが狙える
電気料金は、「一度決めたら終わり」ではなく、「定期的に見直すべき固定費」です。とくに、電力市場や補助金制度が動きやすいここ数年は、「最低でも年1回は、請求書と契約内容をチェックする」ことをおすすめします。
今後も、電気料金のトレンドや政府の支援策、電力会社各社の動向に変化があれば、当社ブログで随時わかりやすく解説・続報記事をお届けしていく予定です。
「うちの会社の場合はどうなるのか?」「具体的にどれくらい削減できそうか?」といった個別のご相談も歓迎ですので、請求書をお手元にご用意のうえ、ぜひお気軽にお問い合わせください。