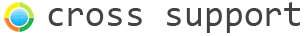先月の速報では、冒頭に「まだまだ残暑が厳しいですね」というお話をさせていただきました。
10月もはや8日。この8日間の中で、大阪の最高気温が30度を超えたのが4日もありました。
ちなみに2023年はどうかというと、10月に最高気温が30度を超えたことは1度もなかったようです。
毎年少しづつですが、着実に気候が変動しているような気がしますね…
今回の原因もLNG
先日、以下のようなニュースが報道各社より伝えられました。
ことし11月に請求される電力大手10社の電気料金は政府による補助金が縮小されることからすべての会社で300円から400円程度値上がりします。
出典:NKH 11月の電気料金 補助金縮小で電力大手10社で値上がり
●https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240927/1000109500.html
残念ながら、11月の電気代についても前月同様、大手10社中8社で値上げ(残り2社は据え置き)となるようです。
それでは具体的な金額を見て見ましょう。
【2024年11月 使用量が平均的な家庭での電気代前月比】
●北海道電力:8,978円 +324円(値上げ)
●東北電力:8,186円 +384円(値上げ)
●東京電力:8,260円 +396円(値上げ)
●北陸電力:7,172円 +334円(値上げ)
●中部電力:8,031円 +403円(値上げ)
●関西電力:7,014円 +390円(値上げ)
●四国電力:7,945円 +374円(値上げ)
●中国電力:7,845円 +374円(値上げ)
●九州電力:6,931円 +375円(値上げ)
●沖縄電力:9,016円 +367円(値上げ)
今回の電気料金上昇の原因は?
普段だと、LNG(液化天然ガス)や石炭の輸入コスト高が値上げの原因…という話になるのですが、11月についてはいつもと事情が異なります。
政府が物価高対策として8月より実施していた電気代補助が、10月をもって中止となります。
例えば低圧契約の一般家庭・企業の場合、10月の電気代は 1kWあたり2.5円の補助が入っていました。
こちらが11月分からは適応されなくなるため、普段の上昇額と比較し各社400円程度の大幅な値上げとなっているのです。
ちなみにLNG等の輸入コストも相変わらずの上昇傾向。このままでは今年の冬の電気代が恐ろしくなってきますね…
※今回、2024年11月分の電気料金については、2024年6月~2024年8月の間に調達した原料のコストが電気料金に反映されます。
世間では石破内閣が発足。近々解散総選挙が実施されるようです。
どのような結果になるにしろ、国民の負担がもう少し軽減されるような政策を打ち出してくれると良いのですがね…