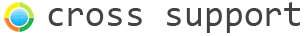気がつけば今年も残りわずか。朝晩の冷え込みがぐっと増してきて、街中ではクリスマスの飾りや歳末セールのポスターが目立つようになってきました。そろそろ暖房を本格的に入れ始めたご家庭や、エアコン・ストーブの稼働時間が長くなってきたオフィス、店舗も多いのではないでしょうか。
その一方で、ここ数年は「暖房をつけたいけれど電気代が怖い」「ガス代の請求書を見るのが憂うつ」という声もよく聞かれます。そんな中、高市早苗首相が今冬の電気・ガス料金の補助を、これまでより増額する方針を示したというニュースが報じられました。
今回は、この「冬の電気・ガス補助金」増額方針の内容を整理しつつ、全国のご家庭・企業にとってどの程度のプラスになるのか、そして補助金に頼りきりにならない電気料金対策について解説していきます。
高市首相が打ち出した冬の電気・ガス料金支援の概要
2025年度冬(2026年1〜3月)に再び補助金を投入
政府は2025年11月、「物価高への対応と生活支援」を柱とする総合経済対策を閣議決定しました。その中で、2026年1〜3月使用分の電気・都市ガス料金を支援する新たな補助金が盛り込まれています。
これは、すでに実施されている「電気・ガス料金負担軽減支援事業」などの仕組みを活用しつつ、冬場の光熱費が最も重くなる時期に、家計と企業の負担を和らげることを目的としたものです。標準的な世帯を想定した試算では、3カ月合計でおよそ7,000円程度の負担軽減になるとされています。
高市首相自身も国会での答弁の中で、「これまでよりも深掘りした支援を行う」「金額も上げる方向で対応する」と発言しており、2025年夏に行われた電気・ガス料金支援(7〜9月使用分)よりも、冬の補助は手厚くなる方向性が示されています。
なぜ冬にここまで手厚い支援を行うのか
背景には、以下のような要因が重なっています。
- 国際的な燃料価格の高止まりと、円安による輸入コスト増
- 再エネ賦課金などの影響も含め、電気・ガス料金の上昇圧力が続いていること
- 暖房需要がピークになる冬は、夏よりも電力・ガスの使用量が増えやすいこと
政府としては、物価高の中でも「電気・ガスだけは止めたくない」という生活の根っこを支えるため、冬の期間に集中的な支援を行うというスタンスです。
具体的な制度・補助額をわかりやすく整理
対象期間と基本的な仕組み
まずは制度の基本的な枠組みを整理しておきましょう。2025年11月時点で公表されている情報をまとめると、概ね次のようになります。
- 対象期間:2026年1〜3月の使用分(検針日により、請求は2〜4月に反映)
- 対象:家庭向け・企業向けを問わず、電気・都市ガスを利用する需要家のうち、一定の条件を満たす契約(家庭および年間契約量1,000万m³未満の企業等)
- 方式:国が電力・ガス会社へ補助金を支給し、各社が毎月の請求額から自動的に値引き(利用者側の申請は不要)
- 対象事業者:大手電力会社・ガス会社に加え、採択された新電力・ガス会社なども含まれる
つまり、利用者側の感覚としては、「いつも通り電気・ガスを使っていたら、請求書に『政府による値引き』が勝手に差し引かれている」というイメージですね。
家庭向け:電気・ガスがどれくらい安くなるのか
資源エネルギー庁の資料によると、2026年1〜3月の電気・ガス料金支援の単価は次の通りです。
- 電気(低圧:一般家庭など)
・2026年1〜2月使用分:1kWhあたり 4.5円 を値引き
・2026年3月使用分 :1kWhあたり 1.5円 を値引き
- 都市ガス(家庭用等)
・2026年1〜2月使用分:1m³あたり 18円 を値引き
・2026年3月使用分 :1m³あたり 6円 を値引き
標準的な世帯モデル(3〜4人家族)で試算すると、3カ月合計で約7,000円程度の負担軽減になると複数の試算が出ています。
もちろん、実際の金額は各家庭の使用量によって上下しますが、「冬の光熱費が1〜2割程度下がる月もあり得る」というイメージを持っていただくとわかりやすいと思います。
企業・店舗向け:高圧契約も対象に
オフィスビルや工場、商業施設などで高圧契約を結んでいる企業・事業所も、今回の支援の対象に含まれます。
電気料金(高圧)については、以下の単価で値引きが行われます。
- 電気(高圧)
・2026年1〜2月使用分:1kWhあたり 2.3円 を値引き
・2026年3月使用分 :1kWhあたり 0.8円 を値引き
例えば、ある月に3,000kWhを使用している事業所であれば、
3,000kWh × 2.3円 ≒ 6,900円
といった形で、月あたり数千円単位の軽減効果が見込めます。需要電力が大きい業種ほど、総額としてのメリットも大きくなります。
都市ガスについても、前述の通り家庭と一定規模以下の企業・事業者(年間契約量1,000万m³未満)が対象であり、飲食店や宿泊業、製造業などガス使用量の多い業種にとってもプラスになりそうです。
申請不要だが、「補助金詐欺」に要注意
制度面で利用者が押さえておきたいポイントは次の通りです。
- 補助金を受けるための申請や口座登録は不要(自動で値引き)
- 請求明細に「電気・ガス価格激変緩和」「政府による値引き」などの項目で記載される
- 過去の支援でも問題になったように、「補助金を受け取るには口座番号が必要」「手数料を払えば補助が受けられる」といった詐欺には要注意
正規の補助は、あくまで電気・ガス料金から自動的に差し引かれる仕組みです。「申請しないと損をする」系の不審なメールや電話には、十分気を付けたいところです。
それでも足りない? 補助金は“追い風”として活用を
ここまで見ると、「3カ月で7,000円も軽減されるなら、ひとまず安心かな」と感じる方も多いと思います。もちろん、冬場の家計・経費を守るうえで非常にありがたい施策です。
ただし冷静に見れば、光熱費が高い家庭や、月に数十万円単位で電気料金を支払っている企業にとっては、補助金だけで根本的な負担が解決するわけではありません。
そこで重要になってくるのが、
- 電力会社・料金プランの見直し(新電力への切り替えも含む)
- 電子ブレーカー導入による契約電力(基本料金)の圧縮
- デマンド監視や設備更新を含めた省エネ対策
といった、中長期目線での電気料金削減策です。
今回の冬の補助金は、あくまで「国からの追い風」。その風をうまく利用しながら、自助努力で電気料金そのものを下げられる体制づくりを進めていくことが、企業・ご家庭のどちらにとっても重要になってきます。
補助金に期待しつつ、継続的な電気料金対策も進めましょう
本記事では、高市政権が打ち出した冬の電気・ガス料金補助金について、その背景や制度の概要、具体的な補助額のイメージを中心にご紹介しました。
ポイントを改めて整理すると、次の通りです。
- 2026年1〜3月使用分の電気・ガス料金に対し、全国で補助金が投入される
- 標準的な世帯で3カ月合計およそ7,000円の負担軽減効果が見込まれている
- 電気は低圧4.5円/kWh(1〜2月)、1.5円/kWh(3月)など、ガスは18円/m³(1〜2月)、6円/m³(3月)といった単価で自動値引き
- 申請は不要で、請求書に「政府による値引き」などの項目として反映される
- ただし補助金は期間限定。新電力や電子ブレーカー、省エネ対策による継続的なコストダウンも並行して検討することが大切
私たちとしても、この冬の補助金には大いに期待していますし、多くのご家庭・企業の一助になると考えています。同時に、「補助金が終わったあとも電気料金を抑え続ける仕組みづくり」こそが、本質的な課題だと感じています。
今後、政府や資源エネルギー庁からは、より詳細な運用方法やシミュレーション例などが順次公開されていく見込みです。実際に2026年1〜3月分の請求が出そろい、「どれくらい安くなったのか」が具体的に見えてきた段階で、当ブログでも再度、実例やグラフを交えた続報記事をお届けする予定です。
その際には、新電力への切り替え事例や電子ブレーカー導入による削減実績などもあわせてご紹介し、「補助金+α」で光熱費を抑えていくためのヒントをお伝えできればと思います。
電気料金の見直しや電子ブレーカー導入について「うちの会社だと、どれくらい削減できそう?」と気になった方は、ぜひ現在の検針票・請求書をお手元にご用意いただき、お気軽にご相談ください。